巧みな文章。米原万里さんの真髄。「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」
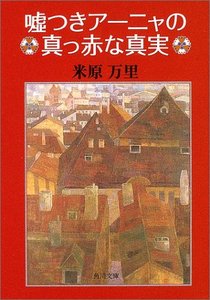
著者 米原万里
これは名作。
エッセイの中で珠玉の作品であった。
現段階で間違いなく2014年のNo 1。
著者の米原万里さんが少女時代にプラハで出会った友人3人のエッセイである。
筆者自身が1960年から1964年まで当時のチェコスロバキア「在プラハ・ソビエト学校」に通った体験を基に書かれている。
登場人物は3人。
リッツァ(ギリシャ)
アーニャ(ルーマニア)
ヤスミンカ(旧ユーゴスラビア)
それぞれ出身国は違えども同じ少女時代を過ごす。
本書は3つに分かれていて
「リッツァの夢見た青空」
「白い都のヤスミンカ」
それぞれ、”少女時代の思い出を振り返る→30年後、米原万里さんが行方を探す旅にでる”との構成になっている。
30年後、東欧の激動で音信の途絶えた3人の親友を探しに筆者が旅にでる話。
解説から一文、引用する。
「本書は20世紀後半の激動の東ヨーロッパ史を個人の視点であざやかに切り取った歴史の証言の書。」
まさにその通り。
本書はただ単純に文章が巧みな作家が少女時代を振り返った本ではない。
政治や国家が進む方向によって個人に何が起きるのかを筆者の体験から見事に切り取っている。
少女時代の思い出→30年後→会いにいく旅との構成の中で、ポイントは空白の30年である。
それは筆者の再会の旅の中で浮き上がっていく東ヨーロッパの激動である。
僕は東ヨーロッパの情勢について、さほど詳しくはないのだが…
正直、心が詰まる思いであった。
米原万里さんは30年経って彼女らに会いにいくのであるが…
彼女たちを少女時代の面影と重ね合わせると空白の30年間が一体彼女たちに何を残し、奪ったのか?と思う。
突然奪われたのではなく、ゆっくりとじわじわ、まるで雫がポタポタと落ちるように失われていったように…。
各人の思い出は非常におもしろい。
例えば、リッツァは非常に"ませている"子供で…
小学校4年生の頃、「男の良し悪しの見極め方、教えたげる。歯よ、歯。色、艶、並び具合で見分けりゃ間違い無いってこと」なんて持論を語る。
※) 僕は27年間生きているがそんな境地には未だ達していない。
他にもリッツァは小学4年生にて”性”に関するオピニオンリーダー的な場面が多々語られる。
アーニャは複雑な思想を持つ。
共産党思想の教科書みたいな思想の持ち主であるのに、一方では貴族のような暮らしをしている。自身は矛盾を感じていない。
そして、何かと不思議な嘘をつく。
ヤスミンカは絵がうまい秀才タイプ。
クラス一番の優等生で、美人で、いつも冷静沈着なヤスミンカ。
米原万里さんと親友になる。
浮世絵が好き、なんて日本人からすると嬉しい一面もある。
ある日の授業でこんな場面がある。
「人体の器官には、ある条件の下では6倍に膨張するものがあります。それは、なんという名称の器官で、また、その条件とは、いかなるものでしょう」
と先生から出題された。
答えは瞳孔なのだが、小学生の女の子はそんな事を知らない。
多感な時期に”ある条件下で膨張する”って事に過敏に反応する。
当てられた生徒はもじもじして答えを言えない。
「わたし、そんな事言えません!!!」なんて言ったりする。
…
そう、男性器を思い浮かべているのである。
(6倍って笑)
先生もコメントに窮する場面であるが…
ヤスミンカは
「先生はこうおっしゃりたいのではないですか?」
「もしほんとうにあなたがそう思っているのなら、そのうち必ずガッカリしますよ」
と顔色一つ変えずに言ってのける。
みなみな個性派揃いでおもしろい。
そして、何より米原万里さんの文章が小気味いい。
(とりあえず読んでみてください、絶対おもしろいから)
本書において、登場人物は皆、祖国について考える。
(というより、考えざるをえない状況にある)
それぞれの愛国心がある。
引用
「大きな国より小さな国、強い国より弱い国から来た子どもの方が、母国を思う情熱が激しいことに気付いた」
「愛国心をかき立てるもう一つの要素がある。それは、故国が不幸であればあるほど、望郷の想いは強くなるらしい」
愛国心ってのは不思議なもので、対になる存在として”同じ国への愛”を持たない人がいなければ存在すらしないものだと思う。
つまり、愛を共有しないが故に生まれる感情なのではないか?
結局の所、宇宙人に侵略されたら”地球愛”が芽生えるのである。
そして、更に不思議なのは、人は必ず人と違うものを愛そうとする。
家族>親戚>所属団体>県>国というように…。
最小単位に近づけば愛は深まる。
それでも、最小単位である個人は同じ愛の扱いをされない。
引用
「異国、異文化、異邦人に接したとき、人は自己を自己たらしめ、他者と隔てるすべてのものを確認しようと躍起になる。自分に連なる祖先、文化を育んだ自然条件、その他諸々のものに突然親近感を抱く。これは、食欲や性欲に並ぶような、一種の自己保全本能、自己肯定本能のようなものではないだろうか。」
我々は異質なものに会う度、自分の原点に回帰するのだろうか?
3人の少女は30年経ち、成長して大人になった。
それぞれ語る…。
印象に残った言葉を引用。
「そういう狭い民主主義が、世界を不幸にするもとなのよ」
アーニャの真っ赤な真実の意味を考えた時、ハッとする。
何が彼女をこうさせたのか?と。
ヤスミンカはこう言う。
「でも、私にはボスニア・ムスリムという自覚はまったく欠如しているの。じぶんは、ユーゴスラビア人だと思うことはあってもね。ユーゴスラビアを愛しているというよりも愛着がある。国家としてではなくて、たくさんの友人、知人、隣人がいるでしょう。その人たちと一緒に築いている日常があるでしょう。国を捨てようと思うたびに、それを捨てられないと思うの。」
…
この言葉の意味を考えるのは、決して簡単なことではない。
タイトルは秀逸。
なにより、少女たちの空白の30年間に思いを馳せると、心揺さぶられる。
自分にとっての愛国心とは?何か。
個人的には顔の見えない国家は好きになれないけど。
(つまり、友人がいるからこそ愛着を持つ)
間違いなくおすすめの一冊。