感情の話
2024年
引き続き、アドラーについて学んでいる。
楽に、且つ、しなやかで健やかな人生を過ごす上では大いに助けになると思う。
"アドラーに出会えたなら、もう大丈夫。"
とはよく言ったものである。
それにしても、
古典的なビジネス書(自己啓発系)がアドラーの影響を受けているのはそこはかとなく感じる。
残滓が残っているというか、
同じ系統性を感じると言っても良い。
さて、
アドラーの言葉で、下記、非常に腑に落ちた。
子供は「感情」でしか大人を支配できない。
大人になってからも、
感情を使って人を動かそうとするのは幼稚である。
これはビビッときた。
確かに、子供は泣き叫ぶ事で、大人を動かそうとする。
泣き叫ぶ = 感情 なのは言わずもがな・・・
ただ、
泣き叫ぶ = 感情 = 怒り
につながりがあり、
・子供が泣き叫ぶ
・仕事で怒鳴っている人
の二つは構図的には全く同じである事に今更ながら気づく。
ああ、恥ずかしい。
個人的に、あまり怒鳴るようなタイプではないのだが、
とはいえども、身に覚えがない事はない。
余す事なく、
自分の感情を発露する事で、
相手を影響下に置く事自体が、自分が子供と同じ事をしていると喧伝しているようなものなのである。
時々、
ショッピングモールで泣き叫んでいる子供を見ると、
まあ可愛いもんだ、と受け流す度量はあるものの、
あれが例えば、大人 (しかも、いい年したおじさん)であると考えると、
眉を顰める所の話では済まない。
思わず、天を仰いで、日本のストレス社会はここまで来たか・・・・。
と嘆く事になるだろう。
トラウマなんてものは存在しない。
アドラー心理学では、トラウマを明確に否定します。
トラウマなんてものは存在しない!
そう語るのである。
実に興味深い指摘であると思うのだが、
実際、トラウマを抱えていて、
今、行動ができない人からすると、
"知った口聞いてんじゃねーよ。こっちの気も知らねーで。"
と毒づきたくなる。
一体、どういう考え方なのか?
実際、
・過去に〜された。
・それが原因で、今は〜できない(したくない。)
なんていう話はいくらでも存在する。
一番身近な例で考えると、
・恋人にふられた。
・もう恋なんてしたくない。
・・・
100人中、少なく見積もっても、20人は経験した事がありそうな話である。
ただ、アドラー心理学では、
トラウマは存在しない、とする。
一体どういう事か?
解釈は、
・トラウマによって行動が制限されているのではない。
・行動を制限するための言い訳として、過去の経験を持ち出している。
→それをトラウマとして、行動しない理由にしている。
と解釈をする。
原因があって結果があるのではなく、
目的があって原因を選んでいる、
と言っても良い。
失恋の話で当てはめると、
①もう恋なんてしない = 目的
②なぜなら、失恋して傷ついたから = 原因
アドラー心理学で考えると、
目的のために原因を選び出しているだけであるとする。
この理論は、
誰しも思うが、
もし、ふられなければ、もう恋なんてしないと思わなかったのではないか?
と突っ込みたくもなる。
自分なりに解釈すると、
この考え方は、もっと広義で捉えるべきであり、
そもそも、フラれて傷つきたくない。との感傷自体に対して、
"そんな直接的に人間の行動は制限されないでしょ?"
との、大前提は必要な気がする。
ただ、
アドラー心理学とは、
・今の自分を変えようとする。
・少しでも今を生きやすくする。
とか、そのような目的のものであり、
決して、精緻な誰も論破できない理論展開を求道するものではない。
つまり、
それがまやかしであったとしても、
・今を楽に生きる為に踏み出す一歩に対して背中を押せれば良い。
のだと思う。
もし、今の自分を変えたい、とか思っている時に、
ある一つの事象が足を引っ張る(= トラウマ)に対し、
それは決して絶対的に存在しうるものではない、と思えるのであれば、
それはそれで、少し気は楽になるような気がするのだが、どうだろう。
数値化できないものを最適化する = センスがある。
「センスは知識からはじまる」
水野 学
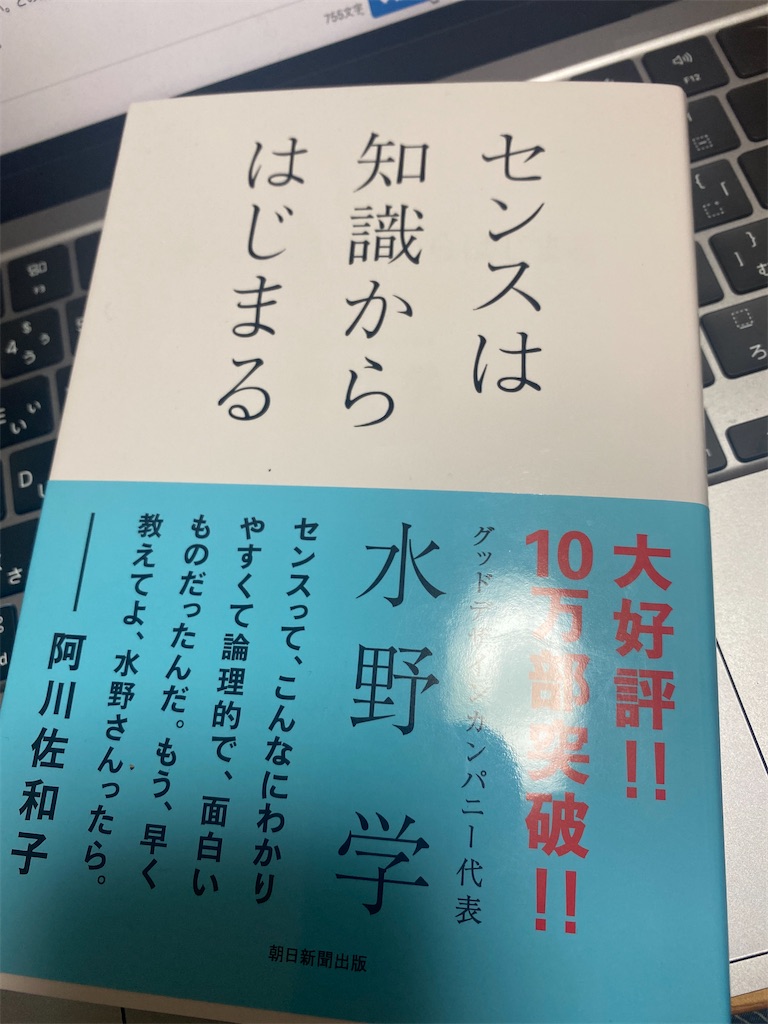
本書の冒頭に、
"センスのよさ”とは、
数値化できない事象のよし悪しを判断し、最適化する能力である。
とある。
(これ自体がセンスないと書けない文章だと思うのだが)
本書は、センスとは知識からはじまるものである、と繰り返し述べる。
個人的には、
・センスが知識からはじまる
よりも、
・センスとは、数値化できないものを最適化する事だ。
と、定義した事に感銘を受けた。
この一文だけで本書を買った価値があったと思う。
何かを一文で定義するのは、
本質が見抜けていないとできない。
センスいいね。
と言うと、
ファッションセンスが一番わかりやすく、
ファッションセンスが良い
=数値化できない、との点では、まさに、腑に落ちたり!
筆者の定義にバチっと当てはまる。
僕は、
このセンスの定義を読んだ時に、
仕事だとどうだろう?
と考えた。
言うまでもなく、
仕事は、
本質的に、数値化が至上命題である。
仕事における数値化できるもの
言うまでもなく、売上→利益の創出である。
極論で考えると、
会社が求める仕事とは、
全てが数値化されているべきであると言っても良い。
では、仕事において、センス = 数値化できないもの
は必要ないか?
と考えると、
おそらくそんな事はないのではないかと思う。
例えば、同僚が売上に繋がらない仕事を一切やらなかったとする。
・・・
おそらくそんな奴は干される。
数値化できないものが重要なことぐらい、
少し考えただけでもわかる。
ただ、今まで、
・数値化できるものについては、数値化する事で追い求めてきた。
その一方、
・数値化できないもの
については、
なんとなく雰囲気で感じ取っていたのだが、
(出世欲が高いと数値化できない事に興味がない人が多い等)
それはつまり、仕事のセンスがない。との解釈になるのだと、
初めて気付かされたわけである。
八日目の蝉
「八日目の蝉」
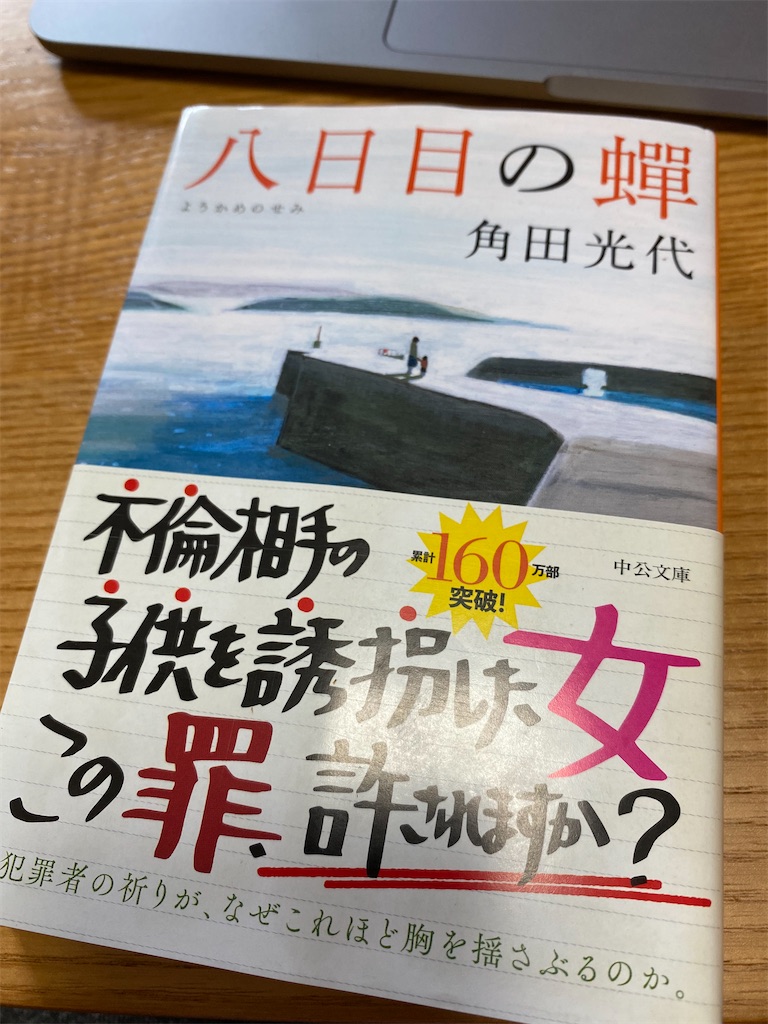
その一言を思い出した時、
あの時、あの瞬間に、
深層に含まれた意味を知る。
その一言を思い出す時、
情景が、人生の物語における一つの帰結として、
目の前に浮かび上がる。
本作はそのような瞬間を描いているのだが、
実に見事。
あっぱれ、感服である。
夕方の、
まばらに人が点在する電車内で、
涙が溢れ出た。
・・・
そう。泣いてしまった。
誇張はなく、
蠢いた感情が出口を探しているようだった。
それほどまでに、
揺さぶられるものが強く、大きい。
あらすじを引用。
逃げて、逃げて、逃げのびたら、私はあなたの母になれるだろうか…。
東京から名古屋へ、女たちにかくまわれながら、小豆島へ。
偽りの母子の先が見えない逃亡生活、そしてその後のふたりに光はきざすのか。
心ゆさぶるラストまで息もつがせぬ傑作長編。
第二回中央公論文芸賞受賞作。
本作は、
不倫相手の子供を誘拐する女の物語。
もちろん、犯罪である。
子供を誘拐した女は、逃亡生活を続ける。
誘拐した時、子供は赤ん坊であったため、
本当のお母さんだと信じて育つ。
本作は、
逃亡する女と誘拐された子供の物語である。
章立てとしては、
・1章が逃亡する女の視点の話
・2章が誘拐された子供が大人になった時の話
となっている。
赤ん坊を誘拐した女の名前は、希和子。
希和子は妻のいる男と不倫をしている。
そして、
不倫相手の男と、その妻の間にできた初めての赤ん坊を誘拐する。
まさに、ドロドロの不倫劇。
ただ、希和子にも斟酌すべき点はある。
それ以前に、不倫していた男と希和子の間にも子供ができており、堕ろしているのだ。
且つ、堕ろした事が原因で調子を崩し、
自分が子供の産めない身体になってしまった、思うようになる。
つまり、精神的に相当苦しんでいたと言ってよく、
背景を全て知っている読者は、
希和子にも情状酌量の余地があるとわかっている。
また、不倫する男も責任感のないゲス野郎であるのは間違いなく。
男の妻も、希和子に対して激烈に攻撃を仕掛ける。
(男を寝とった女なのだから、そういうものだろうか)
読者にとっても、誘拐された側も印象は良くないのが事実である。
ただし、言うまでもなく、
子供を誘拐された側にとっては、許すまじ犯罪だ。
その犯罪の逃避行の中で紡がれていく物語。
そして、帰結。
僕が心揺さぶられたのは、その帰結であり、
冒頭で述べたある言葉を思い出す瞬間なのである。
下記、小説の結末にも触れる。
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
帰結とは、
希和子の逃避行の終わりだ。
本作は誘拐された子供と、との話で進んでいる以上、
希和子は最終的に逮捕されて、
誘拐された子供は両親の元に帰る。
ただし、それまで幾年も過ごしてきた二人の関係は、言うまでもなく本当の親子である。
赤ん坊の頃から育てられているのだから、
母親と信じて育っているのである。
ただ、その関係は、希和子の逮捕と共に打ち切られる。
その為、2章では、
誘拐した母に育てられた女としての人生が語られる。
さて、帰結の話に戻る。
本作の1章の終わり、
つまりは、希和子が逮捕されるシーンの直前。
“どうか、どうか、どうか、どうか、お願い、神さま、私を逃がして。”
との、
希和子の切実なる祈り、で急に幕を閉じる。
そして、2章の語り手である誘拐された子供の視点に映る。
そこでは、
“そのときのことを私は覚えている。”
から始まり、
フェリー乗り場で逮捕される回想がされ、読者は逃避行の帰結を知る。
そして、
希和子が何かを大声で叫んだ。と語られる。
引用する。
ただ、私と引き離されるとき、大声で何か言った。
私は何もしていない、とか、その子を連れていくな、とか、きっとそんなことだ。
・・・
・・・
この時に実は希和子が何を言っていたか?
誘拐された子供は、大人になってその土地を訪れた時に思い出すのである。
その言葉が尋常じゃなく、響く。
胸に詰まる。
その伏線が回収されるのが、140ページほど読み進めた最終盤であり、
そこが物語の帰結である。
希和子は逮捕された瞬間にそう刑事に向かって叫んだのだ。
“その子はまだ朝ごはんを食べていないの。”
・・・
希和子にとって、
逮捕 = 人生の重大事 であったのは言うまでもなく、
言うなれば、もう終わり、なのである。
その時、瞬間、刹那に、反応して出る言葉が、
子供を気遣うそれであった事・・・。
そして、その言葉を思い出した時に、
誘拐されていた子供は、
希和子に愛されていた過去の自分を思い出す。
その帰結が、実に見事で、
心に響き、揺さぶるものがあった。
サピエンス全史 備忘録
「サピエンス全史」の中では、
人々が狩猟から農耕への移行が必ずしも人々を豊かにしたわけではない、
と繰り返し指摘される。
もちろん、当時の人々も豊かさを求めた結果。
安定した生活に支えられた平和な未来。
そこに希望を感じたからこそ、
人々は進んできたのである、と。
引用する。
たしかに仕事はきつくなるだろう。
だがたっぷり収穫があるはずだ!
不作の年のことを、もう心配しなくて済む。
子供たちが腹を空かせたまま眠りに就くようなことは、金輪際なくなる。
だが、歴史は必ずしもその通りにならなかった事を示す。
より楽な暮らしを求めたら、大きな苦難を呼び込んでしまった。
と筆者は指摘する。
人口の増加による食糧難。
定住化による感染症。
備蓄品が巻き起こした奪い合いと闘い・・・。
いずれも、狩猟民族の時代には起こり得なかった事である、と。
では、人類に後戻りする道はなかったのか?
本書の中では、
・長い期間をかけて変わり、狩猟時代を思い出せる人がいなかった。
・人口が増えていた為、既に後戻りできなかった。
とする。
ただ、個人的に思うのは、
人類がとった狩猟から農耕への選択について、
それが正しいものであったと信じたかったのではないだろうか?
自分達と、
その先祖が歩んできた道を否定する事ができなかったのではないか、と思う。
それはその後、現代と重ねて事象を捉えられた時により一層感じた事である。
私たちは、メールとの連絡手段を得た事で、
便利にはなったが、
幸せになったのだろうか?との問いかけだ。
この問いかけは、どちらに分が悪い事でもないような気もする。
ただ、メールにより、人々が自由を得た、との事はない。
メールにより得たものは、
・効率的な連絡手段
・連絡量の増加
である。
この二つは、計算式で言うと、プラスとマイナスの関係で、
結果、プラマイゼロ、と言われると、正直納得してしまう。
端的に言うが、
・手紙を一通書くのにかかる時間
と同じ時間をメールのやりとりに当てたとする。
どちらが親密になれるか?
結果、同じなのではないのか、と思うのである。
ただ、おそらく、結果、同じなんだから、
みんな!メールに縛られない生活をしてこうぜ!
というようには決してならない。
なぜなら、我々はメールにより得られる便利さを知っているからである。
人間は不可逆な生き物であると、改めて感じる。
生み出したものを享受した時、
それを手放すのは、おそらく、生み出すのと同様に難しい事なのである。
法治国家とは神話であり虚構であろうか?サピエンス全史の感想
一つの場所に集合している姿を想像して欲しい。
おそらく、
異様な光景であると感じるに違いない。
ライオンでも、ネズミでも・・・
哺乳類が、10,000を超えて集合するのは、通常では起こりえない。
奇異な事であると思える。
ただ、人類の場合、そうではない。
天安門事件のような政治的事件、
乃木坂46のライブでも、
Jリーグのサッカーであっても、
なんでも良い。
コロナウイルスが流行する中でも、
おそらく日本中のどこかで1,000人程度であれば毎日ぐらいの頻度で集まっているであろう。
根源に何があるのか?
それは、
人々が、
”実在しないものについて語れる事により虚構を生み出せるから”
だという。
参考文献は「サピエンス全史」
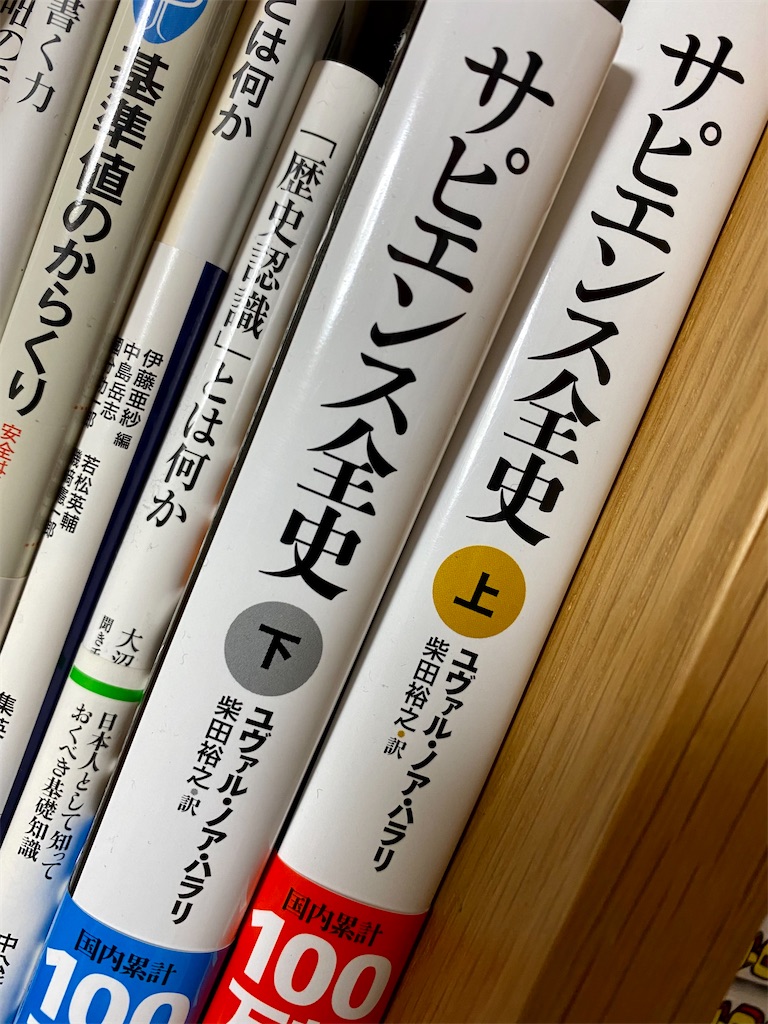
本書の中で、
人類が優れているのは、
実在しないものについても語り共有できる事であるとする。
そして、
その能力こそが、人々に神話を与えたのであると。
神話なくして、
1,000人を超える人々はつながらない。
虚構が人々を接着している、
と本書は主張する。
どういうことか、と考えを巡らすと、
なかなか興味深い観点で世の中の枠組みが揺さぶられた。
例えば、
日本は法治国家である。
日本国が定める法律に反した場合、相応の罰を受ける。
だが、法治国家である証明を、
自分の目で見た事のある人がどれだけいるであろうか?
というのも、
法治国家の証明とは、非常に難しいからである。
法治国家とは、
まず、法の元に誰もが平等に裁かれなければならない。
ただ、実際そうなっているのか、を私は自分の目で確かめた事はない。
無論、法の元に裁かれているニュースは耳にした事がある。
だが、
同じ法律違反をした人間が全く同じように裁かれているとの証明は、
ついぞ目にした事がない。
おそらく、裁きの量刑にはばらつきがある。
極端な話、
犯罪者ながら裁きを受けていない人も、
冤罪での裁きを受けた人もいる。
・・・
これは、
司法も人が運用しているものである、との一事に帰結する。
つまり、人がやっている以上、
判断にはバラツキがある。
完璧な法治国家とは、おそらくあり得ない。
(SFでの近未来的世界でなくては)
また、財力のある者は優秀な弁護士を雇える。
お金の力で、悪人が罪を逃れてのさばっている、とまでは言わないが、
財力により罪を軽くする力を持つ事ができるのだと思う。
(そうではないと、腕利きの弁護士が高い報酬を受け取る理由がない)
法治に対して、お金による抵抗力が強すぎるように思える。
そう考えると、
法治国家とは、一種の虚構である、と思う。
法治国家が虚構ではなくても、
公平で厳密に機能する法治国家は虚構である。
これは、
日本の司法に対する批判ではなく、
人が運営する法治国家とは、
最終的にその段階にしか行き着かないのではないか。
そんなことすらも、考えてしまう。
法治国家の理想型を追いかける途上なのである。
法治国家への叛逆は、
もちろん、法律に縛られない事である。
我々が法律を遵守するのは、
法治国家が法律違反をする者を罰する、と考えているからである。
そこが揺らいだ時、
法治国家は崩壊する。
さて、話を戻す。
人間は、実在しないものを語り共有して、神話とする事ができる。
その能力により、
通常では考えられないような集団行動ができるのである、と。
おそらく法治国家の名の下に、
法の下の平等を信じて、法律を遵守する事もまた神話に支えられている事なのであろう。
小麦が人類を家畜化した?
「サピエンス全史」
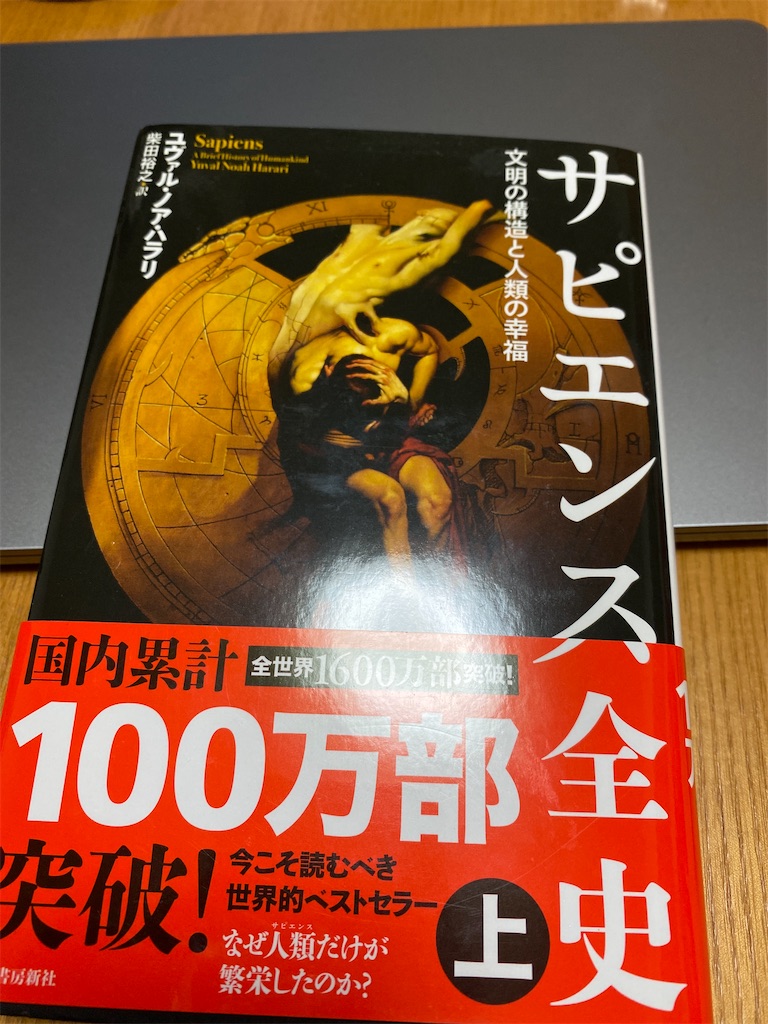
農業革命。
つまり、狩猟民族から、農耕民族への移行。
時が流れるにつれて、
歴史は農耕民族である事を選んだように物語る。
ただし、その選択は、必ずしも進歩の歴史ではない、と本書は語る。
狩猟民族から農耕民族への移行は人類の進歩であるとの考えを
夢想にすぎないと本書は語る。
引用する。
かつて学者たちは、農業革命は人類にとって大躍進だったと宣言していた。
彼らは、人類の頭脳の力を原動力とする、次のような進歩の歴史を語った。
進化により、しだいに知能の高い人々が生み出された。
そしてとうとう、人々はとても利口になり、自然の秘密を解読できたので、ヒツジを飼い慣らし、小麦を栽培することができた。
そして、そうできるようになるとたちまち、彼らは身にこたえ、危険で、簡素なことの多い狩猟採集民の生活をいそいそと捨てて腰を落ち着け、農耕民の愉快で満ち足りた暮らしを楽しんだ。
だが、この物語は夢想にすぎない。
人々が時間とともに知能を高めたという証拠は皆無だ。
~中略~
人類は農業革命によって、手に入る食糧の総量をたしかに増やすことはできたが、
食糧の増加は、より良い食生活や、より長い余暇には結びつかなかった。
むしろ、人口爆発と飽食のエリート層の誕生につながった。
平均的な農耕民は、平均的な狩猟採取民より苦労して働いたのに、見返りに得られる食べ物は劣っていた。
農業革命は、史上最大の詐欺だったのだ。
では、それは誰の責任だったのか?
王のせいでもなければ、聖書者や商人のせいでもない。
犯人は、小麦、稲、ジャガイモなどの、一握りの植物種だった。
ホモ・サピエンスがそれらを栽培化したのではなく、
逆にホモ・サピエンスがそれらに家畜化されたのだ。
衝撃。
この引用部分のみでも、
本書に対しての投資の対価となる。
小麦が人類を家畜化した?
そんな馬鹿な。
ただ、本書を読むと納得する。
小麦が人類に与えたもの、
人類が小麦に与えなければならないもの。
それらを列挙する事で、
小麦が人類を家畜化した、
との今まで一度も考えた事のない論説を明示する。
本書を読んでいて、
右肩上がりの夢想について考えた。
下記、
誰しもに当てはまる話なのかはわからないが、
学校の授業で歴史を学んでいる際、
大前提に歴史から学ぶ、とのお題目が存在していた気がする。
また、歴史は常に正しい選択をするように流れているものであると、
様々な革命は起こるべくして起きて、
今、現代においては、その先にあるものであるかぎり、
積み重ねられた叡智が糧となり、
最も幸せな時代であるに違いない、との夢想があると思うのである。
そのため、
現代に近い時代の方が、遠い時代より優れている、との
根拠なき前提である。
そのため、理由はないが、
故に、幸せな生活をしている、かのように思っていたのだが、
決して、そうではない、
との痛烈な切り返しを知る。
僕自身がそうであるのだが、
今の自分は、結構、色々ともがいて何が正解かもわからない手探りの中で一生懸命に進んできた結果であると思う。
よく考えるとそうなのである。
人類の歴史がたとえ、集合体であろうとも、
その内実は人間の選択であり、
決して、完璧なる選択などできようもないのである。
あくまでも個人が、
一人の人生がそこにあり、
選択をした結果なのである。
ミクロで考えると当たり前の話は、
時にマクロで考えて当たり前ではなくなる。
改めて、そんな事を考えた。