仕事のモチベーションは必ずしも報酬によらない。
必ずしも報酬が全てではない。
人生とは、
・金で得られるものがある
・一方、金で得られないものもある。
至極、当たり前の話。
物事に白黒をつける。
善悪を決めたがる習性により、混乱するのだけれど。
白黒をつけないと非常にわかりやすい。
世の中は、
・お金で得られるものがある。
・一方、お金で得られないものもある。
例えば、
腹ペコで食べる100円のガーナチョコレート。
フルマラソンを走った事を想像して欲しい。
疲れ果てて、糖分を欲している時に食べるチョコレートの味。
僕、個人の話で言うと、
真冬のハーフマラソンを終えた後に食した豚骨ラーメンは史上最高に美味であった。
=絶対にお金では買えない。
あのエネルギーが底を尽きた感覚。
空っぽの身体に暖かいスープが染み渡る感覚。
塩分、脂肪を欲する感覚。
二時間近く走っているのである。
脳が糖分を欲する。
身体が食事を求める。
欲望が、鉛筆削りでギリギリまで細く鋭く削られたかのような、
研ぎ澄まされた食への欲望。
そこにあるものは、
圧倒的な、生物が食事をする時の喜び・悦び・歓び・慶び。
思い出しても震えてしまう。
(つい、熱くなってしまった・・・)
改めて考えると、難しい話ではない。
世の中には、
・お金で買えるものがある。
・一方、お金で買えないものもある。
では、どちらが人生において重要なのか。
結果、どちらも重要なのである。
だが、人は高額な報酬を夢見る。
ただし、報酬とは必ずしも、仕事でのエネルギー。
モチベーションに直結しないらしい。
「人を伸ばす力」
エドワード・L・デシ
リチャード・フラスト
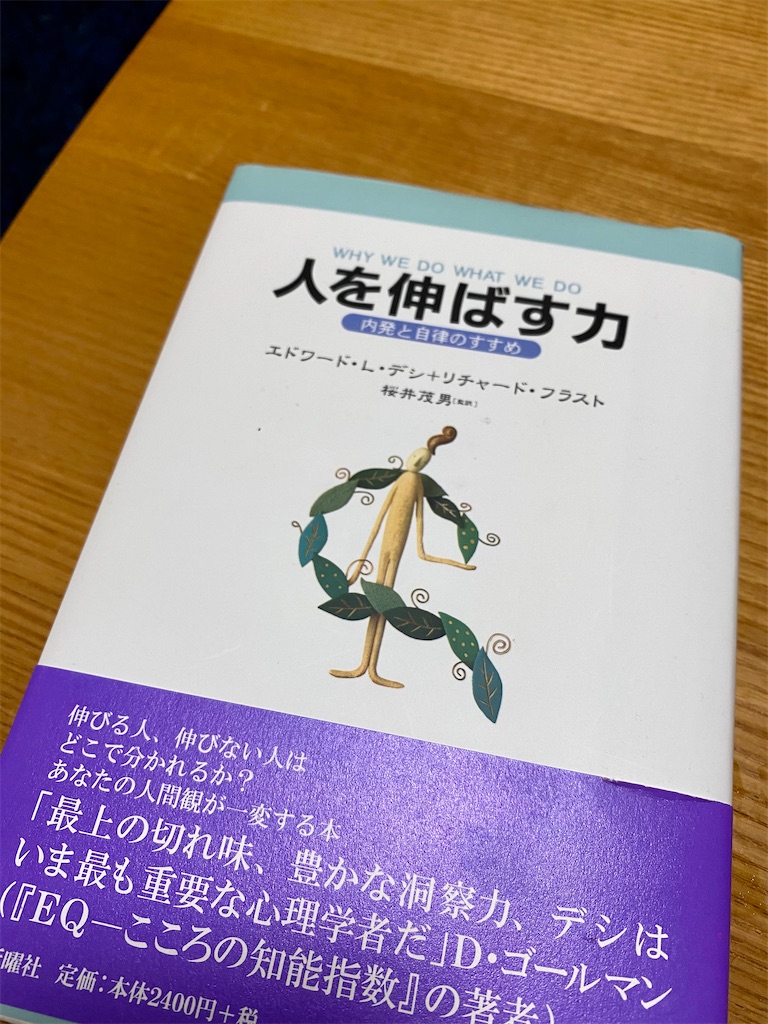
とあるパズルを学生にやってもらう実験についての記述がある。
引用する。
彼らは最初、報酬なしでも喜んでパズルに取り組んでいたのに、
いったん報酬が支払われると、あたかも彼らはお金のためにパズルをやっているかのようにみえた。
金銭という報酬が導入されたとたんに学生たちは報酬に依存するようになったのである。
これまではパズルを解くこと自体が楽しいと感じていたのにもかかわらず、パズルを解くことは報酬を得るための手段にすぎないと考えるように変わってしまったのである。
報酬が内発的動機づけを低下させるというこの結果は、常識を揺さぶる。
つまるところ、
本来楽しかっただけのものが、仕事=報酬を得るための手段に変わってしまった、との話になる。
本書の書き方である、内発的動機づけ、とは、
①自発的にやりたいと思うか。
②強制されてやっているか。
の違いである。
そして、本書の肝は、
内発的動機づけに勝るものはないとし、
人を伸ばす力 = 内発的動機づけをいかに持たせるか、であるとする。
その観点で考えると、
報酬を人参としてぶら下げるのは、
むしろ逆効果である場合がある、との指摘。
よく考えると、納得はできるのだけれど、
実際、本書を読むまではそんな事は一度も考えたことがなく。
一度も考えた事のない見地を人に与えてくれるのだから、
本書が名著として扱われるのも納得できるのである。
小説の境地。
酒は止めたけれども、
何もする気にはなりません。
仕方ないから書物を読みます。
然し読めば読んだなりで、打ち遣って置きます。
私は妻から何の為に勉強するのかという質問を度々受けました。
私はただ苦笑していました。
然し腹の底では、世の中で自分が最も信愛しているたった一人の人間すら、
自分を理解していないのかと思うと、
悲しかったのです。
理解させる手段があるのに、理解させる勇気が出ないのだと思うと益悲しかったのです。
私は寂寞でした。
何処からも切り離されて世の中にたった一人住んでいるような気がした事も能くありました。
言わずと知れた、古典。
夏目漱石の「こころ」からの引用である。
「こころ」
何度読んだ事か。
それでもなお、再読する2022年。
懊悩の深淵に触れて、涙する。
なんでもないような時、
電車の中で涙が止まらなくなった。
今更?と思ったのだけれど、
その寂寞の深さ、果てしなさ、苦しさ。
世の中でただ独り自分が理解されない存在であると、
思い込んだその時の絶対零度の如き孤独。
生きていると小説の読み方が変わると、
よく言われるものだが。
何度も読むべき小説である事は間違いない。
玉虫色に生き方を反映しながらも、
人間が深く迷い込む思想の境地に達している。
改めて書評をしたいもの。
懐かしい。
高校生の頃、夏休みの課題図書として読んで、衝撃を受けた事を思い出す。
変身 カフカ
ある朝、不安な夢から目を覚ますと、グレーゴル・ザムザは、自分のベッドのなかで馬鹿でかい虫に変わっているのに気がついた。
「変身」
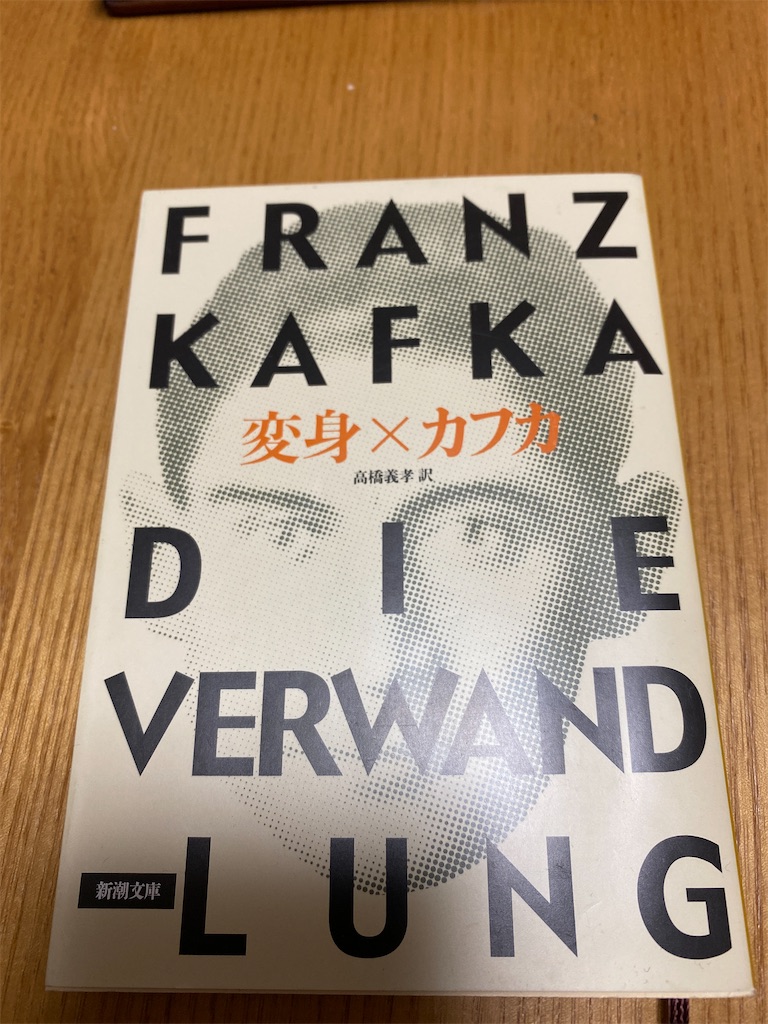
本作は、ある男が朝起きたら虫になっていた。
との一文から始まる世界的に有名な文学作品である。
ある朝、目が覚めたら虫になっている。
との設定は、 現実味のある話ではないのだが、 朝起きた時に虫になっていない保証ってあるんだっけ? と自問自答をした時に、 自分の存在への保証を揺るがす重大な問いとなる。
自分が朝、起きた時、虫に変わっていないと誰が言い切れるのか。
意識がどこかの虫に移ってしまう事が絶対にありえないと、どうして保証できるのか。
カフカの「変身」は、人間の存在を揺らがせる。
意識の所在とは、 確固たる土台を築いているものではないと、改めて思う。
本作は、 小説ではないと達しえない一つの境地にある作品であろう。
虫になった、との設定から、 淡々と虫になった主人公の内面が語られていく物語の進行。
やはり秀逸。
普通、虫になった事に驚きを禁じ得ないはずなのだが、 主人公は、虫になった事を受け入れていくようにすら思える。
僕自身は、本作を大学時代に一度読んでいる。
非常に印象深い小説であった事もあり、 冒頭の部分と結末は明確に記憶が残っていた。
ただ、今、再読してみると、虫になった主人公を、ある日、突然、鬱病になって引きこもりになってしまった人みたいだな・・・
と、重ね合わせて読むようになっていた。
また結末について、 虫になった主人公を、家族がどう扱ったか?
大学時代の僕は、 明確に虫になった主人公の側に立った。
主人公に対する同情、憐憫の念を抱いた。
家族がとった姿勢に対して反発した。 虫になった主人公がかわいそうだと感じた。
10年ほど経った今の僕は、 家族の行動に対して理解を示す事ができた。
下記、少々、結末に触れてしまうが、 なぜ、そのように思ったか? との反芻した時、 人生において棄ててきたものが増えたらではないかと思った。
大学時代の僕は、 今の友達と一生涯、ずっと友達であり続けると思っていた。
付き合っている彼女と結婚する未来を純朴に描いた。
でも、 今はその未来は霧散している。
色々なものを棄てたと思う。
意図して棄てたものもあれば、逆もまた然り。
でも、間違いなく、棄てて前に進んだんだな、と、今は思う。
誰しもが、何かを棄てて、未来を見据える。
その経験が幾重にも重なり、自分でも気づかないうちに心のどこかに沈殿して、 「変身」を読んだ時に感じた事が変わった。
コロナにより、家にいる時間が増えて、 大学時代に読んだ本を再読する日々を過ごしている。
まったくもって使い古された言葉であると思うが、 古典的な名作は読むたびに感想が変わるものである。
司馬遼太郎について
司馬遼太郎の小説に、
彫像に似通うものを感じた。
彫像。
例えば、木彫りの熊をイメージして欲しい。
元はといえば一つの材木が、
彫刻の積み重ねにより、姿を現す。
熊の原型は材木にはない。
材木が彫刻刀で少しずつ削られた到達点として、
生命を宿す熊が現れてくるのである。
ただ、そこに脈動する木彫りの熊は、
たしかな存在感をもって、
生命の飛沫を感じさせるものである。
彫像が創作される過程に、
司馬遼太郎の読書体験との共通点を感じた。
どういうことか?
僕にとって、
司馬遼太郎を読むとは、一種の忍耐が必要なのである。
これが、
(僕は体験した事がないが、想像するに)
木彫りの熊が創作される工程に似通っているように思うのである。
司馬遼太郎の小説は、
綿密で徹底した歴史検証の結晶である。
真偽は知らぬが、
神保町にトラックで乗り付けて史料を収集したとか。
司馬遼太郎が「坂の上の雲」を手掛けた際には、
神保町から日露戦争関連の史料が一切消失されたとか。
僕は、司馬遼太郎記念館でその恐るべき蔵書の夥しさを体感している。
(自宅に6万冊あるというのだから、やはり、一種の異常である。)
その徹底した情報収集の結晶である司馬遼太郎作品は、
言ってしまえば、
地味な時代検証が朴直と積み重ねられていく記述が続く部分があり、
心躍るような、時代の血潮を息吹として感じる叙述が続くのではない。
故であろうが、
僕は司馬遼太郎作品を読んでいる最中、
純粋に面白いと感じているか?と問われると、
疑問が残る。
「坂の上の雲」はその良い例であろう。
僕は、この作品を、読書を始めたばかりの人にはお勧めできないし、
司馬遼太郎作品を初めて読む人にも同様に推薦しない。
読んでいる最中、
決して、面白くてやめられないといったような事はないのである。
だが、司馬遼太郎作品の凄さは、
作品を読み終わった時、
時代と人物像が、
生命を宿し、克明な実像を伴って、自分の中に残っている事である。
そこが、彫像(木彫りの熊)と似ている。
一つ一つの記述(彫刻の動作)は決して派手ではない。
だが、削られていく事で顕かになる実像が、
はっきりとした生命を宿って存在するのである。
最近、読んだのは「国盗り物語」
国盗り物語は、マムシと呼ばれた下克上大名の斎藤道三から、織田信長、明智光秀と物語が続く。
その各々の人生についての考察は、また別であるのだが、
やはり、読んでいる最中には、なかなかの時間を要した。
且つ、いわゆる、娯楽の読書体験ではない。
ページを繰るのに忍耐が必要である。
だが、読み終わって、残る。
自分の中に、確実にある。
斎藤道三が、
織田信長が、
明智光秀が、
時代に生きた確かな胎動が、自分の中で脈打つ。
だから、僕は、司馬遼太郎の小説が好きである。
小人物の扱い方について
偉人は小人物の扱い方によって、その偉大さを示す。
人を批評したり、非難したり、小言を言ったりすることは、どんな馬鹿者でもできる。
そして、馬鹿者に限って、それをしたがるものだ。
「人を動かす」から引用。
小人物の扱い方、とは、非常に難儀な問題である。
たいていの場合、
小人物とは、人をイラつかせる才能を持っている。
(何故か、その才能だけは開花している事が多い。)
社会人になって10年も経てば、小人物が必ずいる。
ただ、小人物の中でも、
マウントをとりたがる小人物ほど厄介なヤツはいない。
人の批評とは、愉悦なのであろう。
社会人になってしばらく経つと、そんな事を思う。
小人物とは、気が小さい事ではない。
人の上に立っている事を確認していないと、心が落ち着かない者の事を指す。
気が小さいものは、陽の当たらない場所でひっそりと暮らすのを良しとするが、
小人物は自分がそのような境遇にいる事を他人のせいにする。
…
もはや、特定の人を思い浮かべているが故、
少々、イラつく。
その扱い方を持ってして、
自分の偉大さを示せとは、誠の難題である。
ただ、難題だからこそ、それができる者は偉大なのであろう。
国盗り物語
庄九郎にとってなにが面白いといっても権謀術数ほどおもしろいものはない。
権ははかりごと、
謀もはかりごと、
術もはかりごと、
数もはかりごと、
この四つの文字ほど庄九郎が好きな文字はない。
これは国盗り物語の中で、
庄九郎(稀代の権謀術数家といえる成り上がりの下剋上大名 斎藤道三)の心理描写である。
後世の人々に“蝮”…マムシと呼ばれた道三。
彼は一介の油売りであった身から、美濃一国を奪い取った。
いわゆる、典型的な下剋上。
日本史の教科書にも、道三の名は下剋上との言葉と同義語であったように思う。
この下剋上は、
現代の社会で考えたときに、
ただの庶民の生まれが総理大臣になったとの話とは置き換わらない。
時代が違う。
時は戦国時代。
権謀術数が蠢く魑魅魍魎の中、一国を切り取るまでの物語。
「国盗り物語」
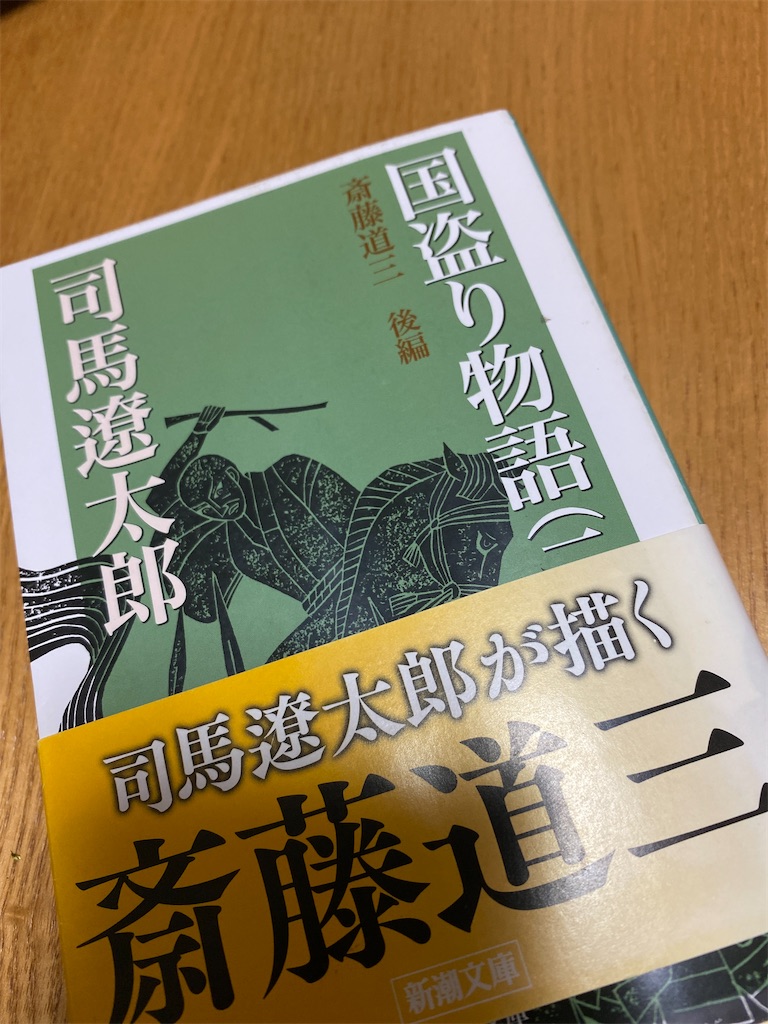
あらすじを引用。
貧しい油売りから美濃国主になった斎藤道三、天才的な知略で天下統一を計った織田信長。
新時代を拓く先鋒となった英雄たちの生涯。
本編は1〜4巻まである長編作品である。
前半は道三の物語であり、
(この道三と信長・光秀は関係性が深く、それが後半へとつながる流れは見事すぎる。)
冒頭に引用した権謀術数のくだりは、鮮烈に印象に残る一文。
おおよそ読んだのは12〜13年前。
大学生の頃。
おそらく、後編の織田信長を目当てに読み始めたと思うが、
権謀術数を分解して、再結合させたこの文章には痺れた思い出がある。
道三の生き様は、強烈で、
その熾烈な生き様が一つの国盗りとの芸術作品になろうとする瞬間を、
道三が自身の権謀術数に酔う形で描く司馬遼太郎は、
やはり歴史家としてだけではなく、文章家として優れている。
その潮流が織田信長に引き継がれていく作品なので、後編も読み終えてからじっくり思い返したい作品。
それから 夏目漱石
小説の最高峰。
人が人である事への苦悩。
どう生きるか?
もしくは、いかに死ぬか。
人間が生きる悩みを真芯で捉えている。
真芯であるが故に、響く。
自己の中にある沈澱物に対して一石を投じるかのように、心がざわめき立つ。
深度ある共振。
だから、一種の疼きとして残る。
・・・
この小説が明治に書かれている事に戦慄する。
100年経った今も、
人間が人間であろうとする泥臭い懊悩は出口がない。
読んだのは、これで3回目である。
「それから」
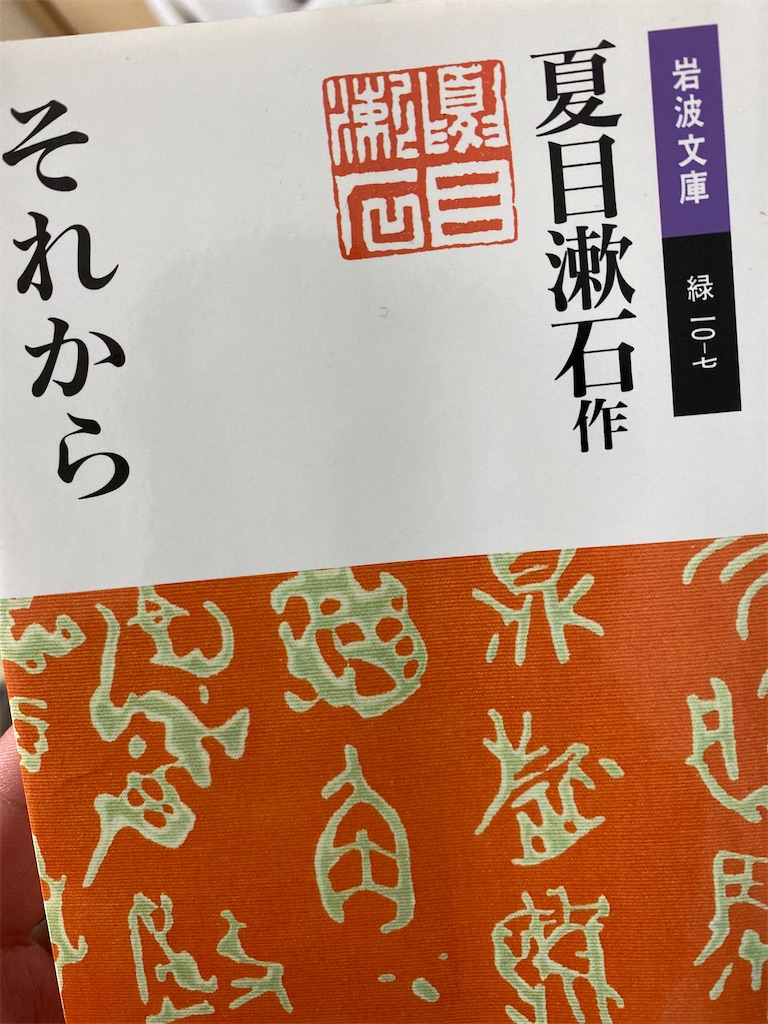
あらすじを引用
恋人はいま親友の妻。
再会、あなたならどうする――。
ラストは、衝撃/納得?
新鮮な問いを投げる、漱石渾身の恋愛小説。
長井代助は三十にもなって定職も持たず独身、父からの援助で毎日をぶらぶらと暮している。
実生活に根を持たない思索家の代助は、かつて愛しながらも義侠心から友人平岡に譲った平岡の妻三千代との再会により、妙な運命に巻き込まれていく……。
破局を予想しながらもそれにむかわなければいられない愛を通して明治知識人の悲劇を描く、『三四郎』に続く前期三部作の第二作。
夏目漱石といえば、
最も有名な作品は「こころ」であろう。
多くの人が国語の授業で一度は聞いた事のある作品。
僕自身は当時、千円札の肖像は夏目漱石だったので(学生が最もお世話になる千円札!)、
どれどれ、お札になるほどの人ならば読んでみようかしらん、と思い読んだ記憶がある。
そして、単純な感想として、普通に小説として読める(意味がわからないといった事がない)ものだな、と驚いた記憶がある。
結構、わかりやすい恋愛小説であり、ここでは多くは語らないが、テーマも身近なのである。
「それから」を読んだ時も同様の事を感じた。
わかりやすく物語を要約するならば、
親友の妻を愛してしまった男の話、なのである。
これって、
今もなお、日本中のそこらで起きている現象であり、
読後の感想が自分だったらどうするか?との、実に陳腐なものに帰結する。
それは、このテーマがいかに普遍であるかを語る。
鍍金を金に通用させようとする切ない工作より、真鍮を真鍮で通して、真鍮相当の侮蔑を我慢するほうが楽である。
この言葉に救われたのは大学生時代の僕である。
本作の高等遊民の概念に憧れた。
今でもその当時の事を鮮明に思い出す。
本作は自分にとって夏目漱石と再会させてもらった作品である。
再読して痺れた。
大学時代に読んだ本とか、
自分の人生に打撃を与えた作品を再読するのは、
実に良いものである。